学芸員が普段の仕事の中で感じたことや、日々のこぼれ話、お気に入りの展示物などを紹介します。
天然記念物の桜
2013.3.25
 お彼岸も過ぎ、暖かい日が多くなってきましたね。広島でも、3月22日に桜の開花が発表されました。
お彼岸も過ぎ、暖かい日が多くなってきましたね。広島でも、3月22日に桜の開花が発表されました。
桜といえば、広島市には、文化財として天然記念物に指定されている桜が二つあります。ご存知の方も多いかも知れませんね。
一つは佐伯区石内にある「神原のシダレザクラ」(県指定の天然記念物)です。昭和48年に指定されました。(樹高約10m、胸高幹囲2.42m、樹齢推定300年以上)
シダレザクラは、エドヒガンという野生種の桜から作られた園芸品種で、枝が垂れ 下がるのが特徴です。寒冷地を好む為、温暖な地で大木があるのは珍しいそうです。花は小ぶりですが濃いピンク色で、隣にある桜と並んで満開となった姿は大変見応えがあります。
下がるのが特徴です。寒冷地を好む為、温暖な地で大木があるのは珍しいそうです。花は小ぶりですが濃いピンク色で、隣にある桜と並んで満開となった姿は大変見応えがあります。
もう一つは、中区江波にある「ヒロシマエバヤマザクラ」(市指定の天然記念物)。平成8年に指定されています。(樹高約14m、樹齢約160年)
ヤマザクラの一種で、通常のヤマザクラの花弁が5枚なのに対し、5枚~13枚の花弁をつける珍しい桜です。京都の桜守・第16代佐野藤右衛門氏により命名されました。江波山公園の中にあり、周辺のソメイヨシノが散りはじめる頃に満開を迎えます。
どちらの桜の木も長い年月にわたり美しい花を咲かせ続けています。少しでも長く愉しめるよう、守っていきたいものですね。
※ヒロシマエバヤマザクラは、ソメイヨシノよりも少し遅めに開花します。江波山公園内は桜の期間中通行規制を行いますので、ご注意ください。
文化財課学芸員 寺田香織/写真上:神原のシダレザクラ。左側が指定樹。右隣のシダレザクラと並んで咲き、迫力があります。写真下:ヒロシマエバヤマザクラ。同じ枝に一重の花弁と八重の花弁が咲きます。
その茶臼山と「ちゃうっす」!
2013.3.5
 先日、職場で山城の話をしていたところ、茶臼山の話になりました。でも私が直感した茶臼山は会話で出てきたものではありませんでした。
先日、職場で山城の話をしていたところ、茶臼山の話になりました。でも私が直感した茶臼山は会話で出てきたものではありませんでした。
そもそも茶臼山とは、茶の湯で抹茶を挽く時に使う茶臼(写真)に山頂部が似ていることから名付けられた山の名称で全国各地にあり、その形状からお城があることが多く、茶臼山城と呼んだりもするのですが…
そこで茶臼山城や茶臼山が広島市内にいくつあるのか気になってしまいました。幸い市内の遺跡を調べる機会があったので、遺跡台帳や地図などをもとに茶臼山城や茶臼山についても調べたところ… 広島市内には遺跡の正式名称としての茶臼山城跡は2か所だけですが、別名を茶臼山城と呼ぶ山城も2か所ありました。これら4か所の山城のある山の名称はいずれもが茶臼山(同じ意味の茶磨山を含む)です。また、山を茶臼山と呼ぶにもかかわらず、そこに位置する山城を茶臼山城という名称でない山城もありました。これらを合わせて市内には茶臼山・茶磨山が少なくとも7か所あり、そ のすべてに山城があることが分かりました。よく知られている西区己斐の茶臼山(写真)は二つが近接しているため、一般に大茶臼山(左黄矢印)・小茶臼山(右赤矢印)と呼ばれています。
のすべてに山城があることが分かりました。よく知られている西区己斐の茶臼山(写真)は二つが近接しているため、一般に大茶臼山(左黄矢印)・小茶臼山(右赤矢印)と呼ばれています。
この他、7か所には含まれませんが、茶臼ガ城跡という別名を持つ城(五菴城跡・安佐北区白木町三田)や、『芸藩通志』に茶臼山 の記載があるものの現在は消滅した山、地元の人が茶臼山と呼んでいる山などがあるようです。
の記載があるものの現在は消滅した山、地元の人が茶臼山と呼んでいる山などがあるようです。
7か所の茶臼山については一覧表を作って見ましたのでご参考までに。この他の市内茶臼山情報をご存知の方はお知らせください。それにしても全国にはいったい茶臼山がいくつあるのでしょうか…
山の名称/城の名称/住所
茶臼山/茶臼山城跡/佐伯区倉重
茶臼山/茶臼山城跡(鷹尾山城跡・茶臼城跡)/安芸区矢野町・安芸郡坂町
茶磨山(牛田山・西山)/戸坂城跡(茶臼山城跡・茶磨山城跡)/東区戸坂他
小茶臼山/己斐新城跡(平原城跡、茶臼山城跡、小茶臼山城跡)/西区己斐町
大茶臼山/立石城跡(釈迦ケ嶽城跡)/西区己斐上・佐伯区五日市町
茶臼山/神宮寺山城跡/安佐北区可部町今井田
茶臼山/阿計玖羅城跡(揚倉城跡)/安芸区畑賀町・安芸郡府中町
文化財課学芸員 玉置和弘/写真上:茶臼(広島市郷土資料館蔵・撮影協力)、写真中:大茶臼山と小茶臼山、いかにも茶臼の形。写真下:太田川の対岸から見た神宮寺山城跡、木が生い茂っているが、頂上には平坦な郭が残されている。
古代米のライスプディング
2013.2.12
 文化財課で育てた古代米を使って、2月16日には洋菓子の先生とともに洋菓子作りを、3月16日には和菓子の先生とともに和菓子作りを福田公民館で行います。「何ができるかなー」と担当も考えて、まずは試作でライスプディングを作ってみることにしました。
文化財課で育てた古代米を使って、2月16日には洋菓子の先生とともに洋菓子作りを、3月16日には和菓子の先生とともに和菓子作りを福田公民館で行います。「何ができるかなー」と担当も考えて、まずは試作でライスプディングを作ってみることにしました。
日本人にはお米を使ったデザートはあまりなじみがないですが、このライスプディングはヨーロッパ・東南アジア・南米など世界各国で食べられている伝統的なデザートなのです。
作り方はとても簡単。ご飯と牛乳・砂糖などを混ぜてひたすら煮詰めていきます(レシピはこちら)。今回は紫黒米と白米を1:9に割合で炊いたご飯で作ったのですが、紫黒米自体に甘みがあるので優しい甘さになります。ライスプディング特有の「ムチッ」とした感触の中に紫黒米の粒々の食感があり、とても美味しいものが出来ました。
現在、菓子の各先生方が古代米のレシピを考え中です。当日は何を作ることになるのでしょうか?
ちなみにあまったご飯で電子レンジでできる煎餅も作りましたが、また次の機会にご紹介。
文化財課学芸員 桾木敬太/写真:完成品。ライスプディングはババロアやオートミールのようなもので、日本人の持つプリンのイメージとは少し違うかもしれません。が、おいしいのは世界共通!
ボランティア「ひろしま歴史探検隊」で活動してみませんか?
2013.2.2
 私たち文化財課と、同じ財団に所属する広島城、郷土資料館の3施設では、広島の歴史や文化財をテーマとする様々な事業を実施しています。この3施設を拠点に活動しているのがボランティア「ひろしま歴史探検隊」です。
私たち文化財課と、同じ財団に所属する広島城、郷土資料館の3施設では、広島の歴史や文化財をテーマとする様々な事業を実施しています。この3施設を拠点に活動しているのがボランティア「ひろしま歴史探検隊」です。
ボランティア「ひろしま歴史探検隊」の特徴は、3施設が実施するボランティア研修会やボランティアを募集する各種事業の中から、自分の興味のあるものだけを選んで参加していただけることです。施設ごとの登録は不要です。
研修会や活動を通じて、まずボランティアのみなさん自身に、楽しみながら広島の歴史や文化財の魅力に触れていただき、そこで得た知識や習得した技術を、地域の活動や各施設の活動の場で披露していただければと思っています。
ボランティア「ひろしま歴史探検隊」の募集は随時行っておりますが、このたび活動内容や施設についてより深く理解していただくために、募集説明会を開催いたします。日時は、平成25年2月16日(土)の午前10時から正午まで、会場は文化財課です。また、2月23日(土)には、文化財課以外の2施設で、ボランティア活動の様子や施設をご覧いただく見学会を行います。(両日とも要事前申込)※詳細はチラシをご覧ください。
ボランティアの経験がない方、ちょっと話だけ聞いてみたい方、どなたでも大歓迎です。ぜひお気軽にご参加ください!
文化財課学芸員 田原みちる/写真:「ハニワ作り」の指導
広島学セミナー講演会「酒~伝統的なものづくりに学ぶ~」
2013.1.24
 広島市未来都市創造財団誕生記念事業として23年度から実施している広島学セミナー。この3月16日(土)に講演会を実施します。講師は東京農業大学名誉教授の小泉武夫先生です。
広島市未来都市創造財団誕生記念事業として23年度から実施している広島学セミナー。この3月16日(土)に講演会を実施します。講師は東京農業大学名誉教授の小泉武夫先生です。
小泉先生は福島県の酒造家のご出身で、醸造学・発酵学の第一人者として研究に取り組んでこられました。また、食文化にも造詣が深く、日本のみならず世界中の「うまいもの」を探求し続けていらっしゃることでも有名です。
実は、私どもが小泉先生をお招きするのは平成22年に続いて2回目です。前回は「発酵食品」をテーマにたくさんの方に聴講していただきました。(小泉先生の語り口はユーモアに富んでいて大変わかりやすいと大好評でした。)
今回は、「酒づくり」をテーマに「酒 ~伝統的なものづくりに学ぶ~」と題して、「酒」の生い立ちや、たどってきた道、風土との深い関係などについてお話いただきます。参加者の募集開始は2月1日から。これを読んだらイベント情報掲示板で詳細をチェック!!
文化財課学芸員 荒川美緒/写真:小泉武夫講師
竪穴住居ミニ博物館オープン
2012.12.15
 11月24日(土)、25日(日)に佐伯区の石内(いしうち)公民館で「第66回石内地区文化祭・公民館まつり」が盛大におこなわれました。
11月24日(土)、25日(日)に佐伯区の石内(いしうち)公民館で「第66回石内地区文化祭・公民館まつり」が盛大におこなわれました。
石内公民館の駐車場には竪穴住居があります。この竪穴住居は、地元の方が、下沖5号遺跡(昭和61年発掘調査)で見つかった住居の跡を参考に10年ほど前に復元されたものです。
春に館長さんから、公民館まつりの時に、竪穴住居を使って弥生時代の展示やイベントができないものだろうかとお話があり、やってみることになりました。住居の中には、弥生時代に使われていた道具の復元品を中心に、住居の中を再現してみました。また、石内地区で発掘された遺跡のミニパネル展を行いました。
多くの方に住居に入って見ていただきました。特に子どもたちは普段は入ることができない薄暗い場所に興味津津。物珍しそうに住居に入って行きました。また、竪穴住居の外では、子供たちをあつめて、古代米炊飯・試食、火起し体験、古代服試着を行いました。
こうしてたくさんの入場者を集めた、2日間限りの「竪穴住居ミニ博物館」は閉館したのでした。



文化財課主任指導主事 河村直明/写真上:公民館まつりの様子(右奥が堅穴住居)、写真下:展示物を熱心に見ている子どもたち
サンフレッチェ広島 祝優勝!広島ビックアーチ付近は昔から戦いの舞台であった?
2012.12.11
 先日、サンフレッチェがビッグアーチで優勝を決め、さらに最終戦でも勝利して有終の美を飾りました。チーム創設時から一サポータとして応援していた私個人も感慨もひとしおです。この場を借りて優勝おめでとうございます!
先日、サンフレッチェがビッグアーチで優勝を決め、さらに最終戦でも勝利して有終の美を飾りました。チーム創設時から一サポータとして応援していた私個人も感慨もひとしおです。この場を借りて優勝おめでとうございます!
今年もビッグアーチは数々の戦いの場となりましたが、このビックアーチ付近が戦いの場となったのは歴史的に言うともっと古く、中世(室町時代・戦国時代)にさかのぼります。戦いがあった理由としては①「今は高速道路の山陽道が通るが中世の折にもこの辺りは山陽道が通る重要な幹線道路があ
ったこと」②「今ビッグアーチ付近は安佐南区と佐伯区の境界近くにあり、安佐南区は昔佐東郡、佐伯区は昔佐西郡と郡の境目でもあったこと」で、東西の勢力の狭間で必然的に戦いが生まれる背景があったのです。
そのため郡境を挟んだ安佐南区沼田地区(伴城、伴東城、伴北城、岸城など)や佐伯区石内地区(有井城、水晶城、串山城、今市城など)には戦いに備えるための多くの山城が位置しているのです。東側からは、安芸武田氏が、西側からは大内氏が攻め、1500年代には戦いが行われたことが文献などに残されています。
この写真は佐伯区と西区との境にある鉄塔から平成4年に沼田方面を撮影したものですが、ここにも茶臼山城という見張りの城がありました。矢印のところにビッグアーチが見えますね。
2枚目の写真は、平成3年に発掘調査中の石内にある有井城です。ここからは豪華な陶磁器が出ていることから、石内の権力者の本拠城だと考えられています。こういった城以外にも戦いの最前線の城や建物がほとんどない城など、様々な種類があったようです。
サンフレッチェは攻撃と守備の絶妙なバランスと選手の個性で優勝を果たしましたが、この辺りの城にもそれぞれの役割があったようです。
文化財課学芸員 玉置和弘
「成岡の王」故郷へ帰る
2012.12.6
 12月20日(木)まで、安芸区の中野公民館で「瀬野川流域の遺跡写真展」が開かれています。瀬野川流域の中野地区を中心とした「成岡A地点遺跡」「成岡B地点遺跡」「三谷遺跡」など6地点のパネル写真展です。
12月20日(木)まで、安芸区の中野公民館で「瀬野川流域の遺跡写真展」が開かれています。瀬野川流域の中野地区を中心とした「成岡A地点遺跡」「成岡B地点遺跡」「三谷遺跡」など6地点のパネル写真展です。
この展示の中で異彩をはなっているのが、古墳時代前期(3世紀後半)の復元人物像です。東広島バイパス建設工事に伴い成岡A地点遺跡で現地調査を行った際(現地調査は平成11年7月から平成12年2月にかけて実施)、第2号古墳からはほぼ完全な人骨から出土しました。土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの松下孝幸先生の鑑定で、この人骨は、身長161.58㎝、老年の男性骨(60歳以上)であることがわかりました。この人物はこの地域の支配者と考えられます。この人骨から、松下先生の監修をいただいて復顔したものが、この人物像です。
現在、この人物像は中野公民館から故郷の山を懐かしそうに見ながらたたずんでいます。安芸区中野地区の方でこの人物像に似ている方がいらっしゃるかもしれませんね。
・「成岡A地点遺跡」など、広島市の遺跡情報については、このホームページの「情報コーナー」→「ひろしま昔探検ネット」をご覧ください。

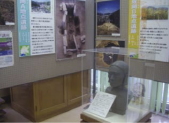

文化財課主任指導主事 河村直明/写真上:復元人物像、下左:成岡A地点遺跡第2号古墳から見つかった人骨、下右:展示風景)
パワフルな古墳人
2012.12.3
 先日、当課のイベント宣伝のためテレビ出演した際、私は当課で以前製作した古墳時代の冑(モデルは中小田第2号古墳出土の冑)と短甲(モデルは城ノ下第1号古墳出土の短甲)を初めて着けました(9月3日のひとことをご覧下さい)。
先日、当課のイベント宣伝のためテレビ出演した際、私は当課で以前製作した古墳時代の冑(モデルは中小田第2号古墳出土の冑)と短甲(モデルは城ノ下第1号古墳出土の短甲)を初めて着けました(9月3日のひとことをご覧下さい)。
その第一印象は「う、重い…」。けっこう足腰にずっしりきます。もちろん本物との差異はあるにせよ、古墳の主たちはこんな重たいものを着けて戦いに臨んでいたのだろうか、と思うと、感心させられました。
そういえば古墳を見るにつけても、その築造にいかに膨大なエネルギーが費やされていたかが一目で分かります。そして、そんなパワフルな人々によって日本はかたち造られていったのです。この甲冑の重みが、私にそれを改めて教えてくれた気がしました。これぞ考古学ならではの体感です!
例え歴史が曖昧でも敬遠するなかれ「古墳時代」。巨大なお墓ばかりに目を奪われてしまいがちなその300〜400年間こそ、実は、日本の歴史上最も魅力的な時代だったのかも知れません。
文化財課学芸員 松田雅之/写真:城ノ下第1号古墳(佐伯区)出土の短甲
- 2013.3.25
- 天然記念物の桜
- 2013.3.5
- その茶臼山と「ちゃうっす」!
- 2013.2.12
- 古代米のライスプディング
- 2013.2.2
- ボランティア「ひろしま歴史探検隊」で活動してみませんか?
- 2013.1.24
- 広島学セミナー講演会「酒~伝統的なものづくりに学ぶ~」
- 2012.12.15
- 堅穴住居ミニ博物館オープン
- 2012.12.11
- サンフレッチェ広島 祝優勝!広島ビックアーチ付近は昔から戦いの舞台であった?
- 2012.12.6
- 「成岡の王」故郷へ帰る
- 2012.12.3
- パワフルな古墳人

