学芸員が普段の仕事の中で感じたことや、日々のこぼれ話、お気に入りの展示物などを紹介します。
咲かない?…まだ咲いています
2012.11.21
 文化財課で今年取り組んでいた変化朝顔。自分でも自宅でタネから育てて8月末にある植物公園の変化咲きアサガオ展への出展を目指していました。ところが、しばらくは順調に育っていた朝顔は猛暑のある日1株、2株…と姿を消し、全部で10株程度あったはずが、なんと半分になっていました。(水やりを怠った為、枯れたようです…)残った株も何やら弱々しくなっているような…。そして花が咲く気配のないまま8月末を迎えてしまいました。
文化財課で今年取り組んでいた変化朝顔。自分でも自宅でタネから育てて8月末にある植物公園の変化咲きアサガオ展への出展を目指していました。ところが、しばらくは順調に育っていた朝顔は猛暑のある日1株、2株…と姿を消し、全部で10株程度あったはずが、なんと半分になっていました。(水やりを怠った為、枯れたようです…)残った株も何やら弱々しくなっているような…。そして花が咲く気配のないまま8月末を迎えてしまいました。
弱らせてしまったせいかも…このままではアサガオ展に出せない!と焦っていると 、株の1つに花芽らしいものが数個ついているのを見つけました。
、株の1つに花芽らしいものが数個ついているのを見つけました。
期待を込めてその鉢を展示することに。どんな花が咲くのか、どんな変化があらわれるのかが実際に咲くまでわからなかったこともあり、花が開くのを心待ちにしていました。9日間の展示期間の最終日、ようやく待望の1輪が咲きました。更にその翌日には(写真上)のような満開状態に!(残念ながら、展示物として皆さまの目には触れませんでしたが…)
失敗も色々ありましたが、今回のことで、変化朝顔の楽しさは実際に育ててみて初めてわかるものなのだと改めて実感したのでした。
 その後は、他の株にも花が咲き、変化の1つである牡丹咲き(雄しべ・雌しべが花びら化して花弁が多くなった状態)のものも出ました。(写真中)どうやら育てて(残って?)いた株のほとんどは遅咲きのものだったようで、成長が遅かったため弱々しくみえていたようです。
その後は、他の株にも花が咲き、変化の1つである牡丹咲き(雄しべ・雌しべが花びら化して花弁が多くなった状態)のものも出ました。(写真中)どうやら育てて(残って?)いた株のほとんどは遅咲きのものだったようで、成長が遅かったため弱々しくみえていたようです。
朝顔といえば夏…と思っていましたが、遅咲きの品種もある変化朝顔は種類によっては今もまだ花を咲かせています。
(文化財課の朝顔については、イベント情報掲示板又は トップページのリンクをご覧ください。)
文化財課学芸員 寺田香織/写真:上…展示した鉢。「青柳葉紅紫撫子采咲」 中…牡丹咲きの状態の朝顔。「青林風雨竜葉白丸咲牡丹」 下…収穫したタネの一部。この段階で、すでに大きさや形、色が違うものもあります。
子供たちのためなら、何にでもなります!何でもやります!
2012.11.1
 文化財課と三滝少年自然の家との共同開催で、今年も「古代キャンプin三滝」が、10月13日(土)~14日(日)の1泊2日の日程で行われました。
文化財課と三滝少年自然の家との共同開催で、今年も「古代キャンプin三滝」が、10月13日(土)~14日(日)の1泊2日の日程で行われました。
このイベントは、今回で8回目となります。古代にちなんだものづくりや古代生活体験などを行うことによって、古代の人たちの生活を知り経験し、古代から続く人と自然とのかかわりについて様々な角度から考えてもらうことを目的としています。また、参加者の仲間づくりの場を提供することも目的のひとつです。
写真は、2日目の古代オリエンテーリィングのガイダンスの途中に突如現
れた古代人です。こどもたちははじめ唖然としていましたが、次第に古代人の話す弥生時代の生活の話に引き込まれて行きました。
古代人の生活体験を前に、現実の生活から古代に連れていく練りに練った?演出のひとつです。どん引きされたらどうしようという恐怖と闘いながら、台本どおり?に演じ、古代人は山へ帰って行きました。
(古代キャンプの様子は本ホームページ「イベント情報掲示板」をご覧ください。)
文化財課主任指導主事 河村直明/写真:上…古代人乱入 下…古代人の話に引き込まれる参加者
シカたない・・・ことはなーい
2012.10.24
 文化財課では東区福田の休耕田を耕し、古代米の栽培とそこに生息する絶滅が危惧されるハッチョウトンボなどの生き物を観察をしてきました。米作りの右も左もわからない担当達が手探りで古代米を栽培し、バケツ稲と同じく2年目を迎えました。たった1年ですが経験というゆとりがあり、苗づくりや田んぼアートにも挑戦するなどさらなるステップアップを試みてきました。
文化財課では東区福田の休耕田を耕し、古代米の栽培とそこに生息する絶滅が危惧されるハッチョウトンボなどの生き物を観察をしてきました。米作りの右も左もわからない担当達が手探りで古代米を栽培し、バケツ稲と同じく2年目を迎えました。たった1年ですが経験というゆとりがあり、苗づくりや田んぼアートにも挑戦するなどさらなるステップアップを試みてきました。
順調に稲も育ち収穫を1週間後に迎えたある日、田んぼにシカが入ったとの連絡を受けました。様子を見に行くと、田んぼに植えた黒米の3分の1ほどが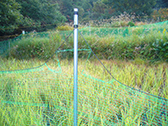
見事に食べられていました。「電気柵も防獣ネットもしていたのに・・・」とトホホな思いで、後ほど電気柵のケーブルを見ると、なんとケーブルが何者かに刃物で切られていたのです。そのため、電気が通じずシカがネットを越えやぶり田んぼに入れたのです。動物だけにやられるならシカたないとあきらめられますが、心ない人もいたものです。米作りにとって虫も怖い、動物も怖いとは思っていましたが、人が一番いけないですね。
後日、参加者の皆さんと楽しく稲刈りはできましたので、まあよしとしましょう。
文化財課学芸員 桾木敬太/写真:上…穂の先だけ見事に食べられました 下…破られた網
油断大敵!恐るべし虫パワー~古代米のバケツ稲栽培~
2012.10.6
 文化財課で取り組んでいる「古代米のバケツ稲栽培」。昨年は初めてだったので失敗もありましたが、秋には無事収穫することができました。二年目となる今年は要領もわかっているので、昨年以上の出来を目指してスタートしたのですが…。
文化財課で取り組んでいる「古代米のバケツ稲栽培」。昨年は初めてだったので失敗もありましたが、秋には無事収穫することができました。二年目となる今年は要領もわかっているので、昨年以上の出来を目指してスタートしたのですが…。
春、昨年収穫した種籾の芽出しをしてバケツに蒔きました。出芽後の成長は昨年以上で、バケツいっぱいに青々と繁る稲を見て収穫への期待はふくらみました。
初夏になり、稲の葉を食べるイチモンジセセリの幼虫や卵などが葉にちらほら見られるようになりました。無農薬栽培に取り組んでいるので、昨年は
毎日時間をかけて葉を一つ一つチェックし、丁寧に駆除していました。とこ
ろが、今年は稲のあまりに順調な成長ぶりに安心し、少し油断してしまった
のです。
お盆休みが明け、稲を見て絶句…!水はきらさないようにしていたものの、爆発的に増えた幼虫たちによって、あれだけ繁っていた葉が見るも無残に食べつくされようとしていたのです!慌てて、おびただしい数の幼虫を駆除したものの、稲はすでに瀕死の状態…。「今年は終わった…」と一時はあきらめかけましたが、古代米の強い生命力のおかげでなんとか復活し、稲穂も実ってきています。
田んぼと違い、稲の害虫にとって天敵のいない街中のバケツ稲。イチモンジセセリ、カメムシ、イナゴなど…稲をねらう虫たちとの闘いはもうしばらく続きそうです。
文化財課学芸員 田原みちる/写真:上…スズメ対策もバッチリ!? 下…イチモンジセセリの幼虫
考古学用語もささやく?
2012.9.14
 先日の学芸員のひとことで「地名はささやく」というのがありましたが、確かに昔からの地名からその場所の地形などを類推することが出来ますよね。それって歴史や考古学の用語もなんです!
先日の学芸員のひとことで「地名はささやく」というのがありましたが、確かに昔からの地名からその場所の地形などを類推することが出来ますよね。それって歴史や考古学の用語もなんです!
昔の人が創作した名称・用語は漢字で見た目の造形・形状から意味を凝縮して表現します。考古学の出土品や遺跡などはかなり想像力を膨らませてイメージできるものも数多くあり、中にはセンスのある素晴らしいネーミングがあります。
そこで問題です。石で出来たこの資料、昔の人は「何々」石と名付けたでしょう?幼児が洗髪時に付ける「シャンプーハット」石?違います!答えは車輪石です(写真は中小田第1号古墳出土)。余談ですが私も子供が小さい頃、シャンプーハットを見るたびに車輪石を思い浮かべていたのです。
真ん中に穴があいていて見た目「車輪」に見え、放射状の模様がスポーク
をイメージできるということで江戸時代に名付けられたようです。でも資料そのものは、車輪に見えるだけで、車輪の機能とは全く関係ありません。
車輪石と同じように古墳から出てくる同じようなものに鍬形石があります。これは、農具の「鍬」の形をした石という意味です。確かに、鍬の金具部分がそれとなく似ていますね。ちなみに、鍬形は兜の左右に飛び出した角のような飾りの名称にも用いられ、そこから似た角を持つ昆虫をクワガタムシと呼ぶようになったという説もあります。
古墳時代のネーミングでは「四隅突出型墳丘墓」(四つの隅が飛び出している丘のようなお墓)「三角縁神獣鏡」(縁が三角の形をし、神獣が描かれている鏡)などや、有名なところでは「前方後円墳」もそうですね。昔の人のネーミング力に現代人は脱帽です。シャンプーハットをまだ利用している幼児の皆さんも脱帽してくださいね!
文化財課学芸員 玉置和弘/写真:上…車輪石 下…シャンプーハット着用中
ケーブルテレビに出演!
2012.9.3
 文化財課では、発掘や調査で分かったことを広く市民の皆さんに知っていただくため、様々な体験型のイベントや講座・展示を行っています。
文化財課では、発掘や調査で分かったことを広く市民の皆さんに知っていただくため、様々な体験型のイベントや講座・展示を行っています。
事業を知っていただくために広報活動もします。チラシを作成して、公民館や図書館等に置いたり、「市民と市政」や「to you」に記事を載せてもらったりします。ラジオやテレビに出演することもあります。
先日、ふれあいチャンネル(ケーブルテレビ)の広島市未来都市創造財団PRの時間に、秋におこなわれる文化財課主催事業の広報をすることとなり、収録が行われました。みなさんに内容をより理解していただくために、パネルや道具を持っていっ たり、服装に工夫を凝らしたりして出演しました。
たり、服装に工夫を凝らしたりして出演しました。
しかし、あまり慣れてはいないので、緊張しっぱなしでした。編集をしてもらってどのように放送されるのか心配です。
私の出演したものは放送されたのですが、他の学芸員が出演した(写真)ものは、9月3日(月)12:20から、「ふれあいチャンネル」で放送されます。また、文化財課の今後の主催事業等については、このホームページの「イベント情報掲示板」に掲載していますのであわせてご覧ください。今後もいろいろな事業を予定しています。
文化財課主任指導主事 河村直明/写真:<ふれあいチャンネル>スタジオでの収録風景
広島学セミナー・「広島の文化財講座」
2012.8.31
 著名な研究者から歴史や文化財について学ぶ「広島の文化財講座」も今年で6年目を迎えました。手前みそながら、毎回たくさんのお申込みを頂戴しありがたい限りです。
著名な研究者から歴史や文化財について学ぶ「広島の文化財講座」も今年で6年目を迎えました。手前みそながら、毎回たくさんのお申込みを頂戴しありがたい限りです。
今年度の第3弾として、10月6日(土)に「講座 三村教授に学ぶ『広島の神楽』」を開催します。講師は、神楽研究の第一人者、広島工業大学教授の三村泰臣先生。神楽の歴史、世界観などについて学び、郷土の民俗芸能と人とのあり方について考えます。
現在、申し込み受付中です。参加ご希望の方は、ぜひご応募ください。(往復はがきでお申込みください。9月15日(土)の消印まで有効です。詳細はイベント情報掲示板をご覧ください。)
10月13日(土)には、第4弾として「古瀬教授と行く歴史探訪フィールドワーク『遺跡の小宇宙 三次』」を予定しています。こちらは、広島大学大学院文学研究科教授の古瀬清秀先生と三次市内の代表的な史跡を巡ります。あわせてよろしくお願いします。
文化財課学芸員 荒川美緒/写真:安芸十二神祇『荒平舞』(三村泰臣先生提供)
地名はささやく
2012.8.14
先日、上根峠(安芸高田市八千代町)でフィールドワークを実施しました。そのとき、その一帯の地名を調べて感じたことを紹介します。
上根峠の東側の「霧切(きりきり)谷」。峠の上を源流として北東へ流れる簸川沿岸に立ち籠めた霧が、そこで途切れるからそう付いたといわれます。しかし『芸藩通志』では「キリキシ谷」となっています。「キリキシ」といえば、ふと中世の山城で敵が登れない様につくった急斜面「切岸」が連想されます。しかも、この付近には「火番谷」「馬場」といったものものしげな地名も。上根峠は高低差約80mの急崖で、広島市安佐北区可部方面から八千代町方面に攻め上ろうとする軍勢を阻む、天然の切岸にも似ており、そうした防御に用いられたとする文献もあります。それでは「キリキシ」と「霧切」、どっちがもとの地名なのでしょうか?
次に上根峠の南西、根谷川の峡谷を隔てた備前坊山中腹にある、向山本郷の「河原」。山腹に「河原」とは何故でしょうか?実は、向山本郷一帯の緩傾斜地は、根谷川の峡谷が刻まれる以前は、簸川の源流部の一つとして現在の簸川沿岸の平地とつながっていて、当時簸川が運んだ礫の層も確認されています。すると、かつて人々がこの地を切り開いた際、たくさんの礫が出てきたので「河原」と呼んだのでしょうか?
もう一つ、時は平清盛が活躍した平安時代末、現在の北広島町千代田一帯に壬生荘という荘園が出来ます。その南の境とされたのが「坂山峯并可部庄祢境大須々木尾鼻」。そのうち「坂山峯」は上根峠のことではとする説があり、「可部庄祢(ね)」は現在の「可部」「根之谷」「上根」「下根」といった地名に引き継がれています。では「大須々木尾鼻」は?おそらく市民のほとんどの方と同様、私も聞き慣れない地名だったのですが、地図を眺めていると、安佐北区大林西部のまさかと思える様な山中に、「大薄(おおすすき)」という地名があったのです!調べてみるとそれは江戸時代の文献にも現れ、備前坊山から南に続くその辺りの山を「大薄山」といった様です。「大須々木尾鼻」とは、大薄山から延びる尾根(尾鼻とは、尾根の先といった地形のことと推測します)のどれかのことだったのでは?そう思いつつ山深きその地に立つと、地名の生命力を感じました。
どれも謎かけの様にはっきりしませんが、地名の向こうに、実はささやかな「真実」が隠れているのかも知れません。
文化財課学芸員 松田雅之/写真:大薄から白木山への眺め
- 2012.11.21
- 「咲かない?…まだ咲いています」
- 2012.11.1
- 子供たちのためなら、何にでもなります!何でもやります
- 2012.10.24
- シカたない・・・ことはなーい!
- 2012.10.6
- 油断大敵!恐るべし虫パワー~古代米のバケツ稲栽培~
- 2012.9.14
- 考古学用語もささやく?
- 2012.9.3
- ケーブルテレビに出演!
- 2012.8.31
- 広島学セミナー・「広島の文化財講座」
- 2012.8.14
- 地名はささやく

